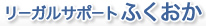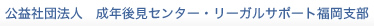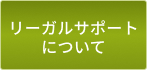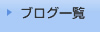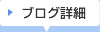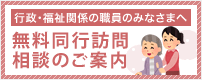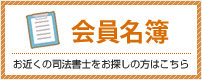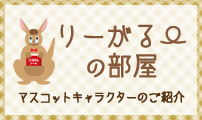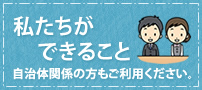[2025/04/29]

令和6年度権利擁護シンポジウム「パネルディスカッション」レポート
令和6年度権利擁護シンポジウムレポート
令和7年3月7日(金)13時から、(公社)成年後見センター・リーガルサポート主催の令和6年度権利擁護シンポジウム「チームによる権利擁護支援を考える~権利擁護支援チームの役割と今後の方向性・課題~」がAP東京八重洲にて開催されました。
当シンポジウムは、司法書士だけではなく福祉従事者や市民後見人の方にも非常に注目されており、毎年、定員を超える参加申し込みをいただいています。
今回取材したパネルディスカッションは、コーディネーターが司会進行を務め、パネリストがディスカッションを行い、アドバイザーが都度話をまとめる形式であったため、非常に聞きやすく、ディスカッションの内容に集中することができました。登壇者の方々を以下に紹介します。
パネリスト
・丸山広子氏
(社会福祉法人上尾市社会福祉協議会上尾市成年後見センター専門相談員)
・秋野美紀子氏
(社会福祉法人新城市社会福祉協議会相談支援課長 兼 新城市
権利擁護支援センター長)
・安樂美和氏
(当法人利用促進法対応委員会委員)
アドバイザー
・安藤亨氏
(豊田市福祉部よりそい支援課地域共生・社会参加担当長)
コーディネーター
・西川浩之氏
(当法人副理事長)
パネルディスカッションでは、成年後見制度の運用において、地域で支援の中心となる中核機関の役割や、制度をうまく活用するための工夫・課題が紹介されました。福岡支部からは安樂美和会員がパネリストとして登壇し、専門職後見人として経験した事例を紹介しました。複数の課題が取り上げられ、どれも興味深いものでしたが、特に気になったものを紹介します。
まず、成年後見制度を利用する本人を支援するチームづくりの課題として、安樂氏は、司法書士の立場から、支援する側同士の関係がうまくいかない場合や、本人・家族が支援を拒否することで、支援が進まない事例を紹介しました。90代の独居高齢者のケースでは、親族との関係悪化や支援者間のコミュニケーション不足により、支援が進まなかったとのことです。このような困難なケースにおいては、支援者が孤立せずにチーム全体で連携できる支援体制づくりが必要とのことです。
続いて、中核機関の役割といった観点で、秋野氏から新城市の取組みについて紹介がありました。新城市では、まず中核機関が関係機関と協力して事前の評価・調査を行い、必要な支援の方向を話し合います。これにより、支援チームが成年後見人の役割やできることを理解し、支援活動にうまく繋がるそうです。
また、丸山氏より、上尾市の取組みが紹介されました。専門職後見人や親族後見人からの相談があった場合、地域包括支援センターと連携し、支援者と後見人を繋げます。後見人には事前の情報共有や丁寧な案内も行います。このように、支援者と後見人とで共通の理解を持つことが、良いチームづくりに役立つと話されました。
成年後見人の担い手不足に関する課題では、安樂氏は、地域による差があると述べています。都市部では専門職が多くても、情報が不足していて引き受けをためらうケースもあります。申し立て時に提供される情報が不十分であるため、不安に思い、支援が難しくなることが多いとのことです。
秋野氏によると、新城市では、後見人候補者との事前面談を重視し、ご本人の価値観や希望を確認し、後見人候補者との相性をチェックします。面談を通じてご本人の不安や疑問を解消して、後見人が安心して役割を果たせるようにすることが重要だと強調しました。
また、丸山氏は、支援チームは、結成した後も継続的に連絡を取り合い、状況に応じて柔軟に対応することが重要だと述べました。特に複雑なケースでは、そうした体制を構築し、維持していくことが、支援の成功に繋がるとのことです。
成年後見制度への理解に関する課題では、秋野氏は、担い手不足に関する課題と同様に、本人との事前面談の必要性を強調しました。成年後見制度を安心して利用してもらうために、直接話をし、不安を解消します。また、本人の状況が変化することに応じて支援体制の見直しや、新たな連携が必要になります。たとえば知的障がいをもつ方の事例では、家族がオンラインで支援に関わる工夫を行い、家族の安心に繋がりました。
最後に、安藤氏による総括も紹介します。安藤氏は、成年後見制度における支援の中心には常に本人の意思があるべきで、支援チームがどれだけ動いても、それが本人の利益や希望に沿っていなければ意味がないと強調しました。チーム支援では、「誰のための支援なのか」という視点を見失わないことが重要であり、また、支援チームとしての連携も不可欠とのことです。個々の専門職が連携しながら、本人にとって最適な支援を提供していく体制づくりが求められると締めくくりました。
以上の他にも、シンポジウムでは様々な課題やテーマが取り上げられ、ブログでは紹介できなかった事例や地域ごとの取組み等を、パネリストの方々にお話いただいています。本シンポジウムは、(公社)成年後見センター・リーガルサポートのホームページ(https://legal-support.or.jp/general/)にて令和7年6月30日までオンライン視聴が可能です。期限が限られていますので、気になった方はぜひご視聴ください!